【ADHD+ASDの長男】小学校どうする?就学前相談と見学を経て我が家が出した答え。
こんにちは。
我が家の長男は、ADHD+ASDの診断ありの年長さん。
来年から小学校ということで、
市の就学前相談や学校見学を経て、
現時点での「我が家の結論」をシェアしようと思います。
「あれ?」と思い始めたのは2歳頃から
2歳を過ぎたころから、
「ん?ちょっと他の子と違うかも?」と
違和感を覚える場面が増えました。
そこから発達相談を経て、年中で児童精神科を受診。
詳しい経過については、以下の記事にまとめています👇
▶ 年長で診断】ADHD+軽度ASDの息子|発達障害に気づいたきっかけ
▶ 児童精神科初診レポ】年長息子がADHDと診断されるまで
就学前相談の流れとスムーズだった理由
市の就学前相談では、教育委員会の担当者さんと心理士さんと面談。
事前に児童精神科で発達検査を受けていたので、
相談もとてもスムーズに進みました✨
うちの地域は児童精神科の予約が1年以上待ち💦
それでも間に合ったのは本当にラッキーだったなと思います。
小学校との連携&支援級の見学へ
就学前相談の情報が小学校にも伝わり、
夏休み中に「保護者面談をしましょう」と連絡が。
まずは親だけで面談を行い、
その後、支援級の見学に長男も一緒に参加しました。
さらに、学校側が幼稚園にも見学に行ってくれて、
本当に手厚くサポートしていただき感謝しています。
支援制度はいろいろ。でも、自治体によって全然ちがう!
ひとことで「支援」といっても、実はいろんな種類があります。
例えば👇
- 支援学校(特別支援学校)
- 支援級(特別支援学級)
- 通級指導教室(通常級に在籍しながら、週に数回支援を受ける)
今回、我が家が検討したのは「支援級」ですが、
選択肢としては「通級」も検討していました。
ただ、うちの市では、
すべての小学校に通級があるわけではありません。
たまたま予定している小学校には
支援級も通級もある学校だったので、
環境としては本当にラッキーだったなと感じています。
支援のあり方は自治体ごとに違うから、確認がめちゃ大事!
実はこの支援の内容や体制は、
本当に「自治体によって全然違う」んですよね。
- 通級がある学校・ない学校がある
- 支援級の分類や人数もバラバラ
- 相談窓口の対応も市区町村によって温度差あり
なので、
まずは自分の住んでいる地域のサポート体制をしっかり調べること!
これがめちゃくちゃ大事だと痛感しました。
私も「うちの市ってどうなんだろ?」と不安に思っていたので、
就学前相談や小学校の見学を通して実際の状況が見られたのは大きかったです。
通う小学校の支援体制は…
うちの市では、すべての小学校に通級があるわけではありません。
でも、たまたま通う予定の小学校には通級も支援級もある学校でした。
支援級は
- 知的
- 情緒
- 身体
の3クラスに分かれていて、それぞれ全学年合わせても数人ずつ。
見学時の印象は「少人数でしっかり見てもらえる」感じでした。
支援級は、ほぼマンツーマンで先生が見てくれる環境。
逆に言えば、ぼーっとしたりサボったりはできなそう🤣
でも、先生がすぐ気づいてフォローしてくれるのは本当に安心。
週の授業数の半分を目安に交流級(通常級)で授業を受けるようです。
一応、学年の途中で支援級と通常級移れるとのことですが、おすすめはしていないとのことでした。
我が家が出した結論:まずは支援級からスタート
最終的には「親の判断にお任せします」とのことでしたが、
私たちは、支援級スタートで様子を見ることに決めました。
理由はこんな感じ👇
- まずは学校生活や人との関わり方に慣れてほしい
- 環境に慣れてから普通級への移行の方が精神的な負担が少ない気がする
- 次男が3年後に入学予定なので、その前に普通級に移れるのが理想
無理せず、子どものペースで。
焦らず、でも希望は持って。
そんな想いで、来年からのスタートを迎えたいと思います🌱
最後に
発達の凸凹があると、就学に向けて不安が尽きないですよね…。
でも、早めに動いて情報を集めることで、
子どもに合った選択が見えてくると思います🌸
もし今、同じように悩んでいる方がいたら、
この体験が少しでも参考になりますように。

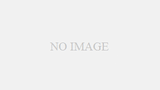
コメント